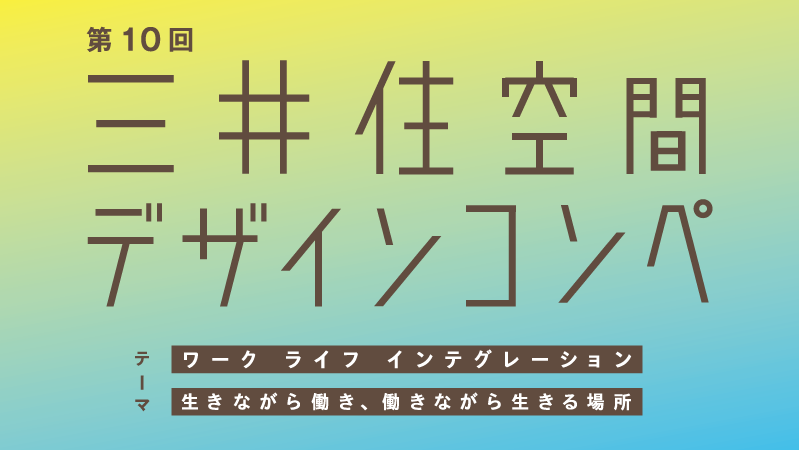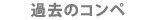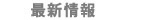審査講評
光井純
建築家/光井純&アソシエーツ建築設計事務所・ペリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン代表,日本大学客員教授

ITの革新的な発展によって働くことと暮らすこと,そして遊ぶことの境界が曖昧になりつつある時代において,住空間の未来はどのように変化していくのかを問うコンペであった.家族を育み幸せを追求する暮らしを営むこと自体は,人が人である限りどんな先の未来でも変わらない.しかしながらIT技術の進化に伴って,「働く」ことがどんどん家庭の中に入り込んでくる.どこに境界線を引くのか,引くこと自体が必要なのか,第三者は家の空間の中に入って来るのか来ないのか,どの応募案も真剣に考え提案を行なっている.今回も非常に面白いコンペとなった.そして審査委員自身,仕事と暮らしに関する価値観が問われるコンペでもあった.
三井住空間デザイン賞の川見案は他にもいくつかあった土間入り案の代表案である.特徴的なのは玄関脇に個人エリアとして小さな書斎を設けたことである.土間を介して仕事の場と家族の団欒の空間を緩やかに分けている.いくら家の中で仕事をするとはいえ,ONとOFFの心理的な分割は必要としている.また,水回りを中心に回遊動線を展開し,リビング,寝室,ダイニングキッチンをバランスよく,巧みに配している.たいへん優れた案となっており完成が楽しみである.
優秀賞の池田案は非常に明快な空間構成が目を引いた.家族が集まる井戸端空間が魅力的である.しかしながら中央空間と周囲を取り巻く空間の段差が,空間を不連続にさせている印象が強く,使いにくいのではという意見もあった.床の段差が持つ住空間での影響力に,もう少し配慮があるとよかったと思う.
佳作の中では生駒案にたいへん惹かれた.大型の造作家具によって空間を分断しながら緩やかに繋ぐコンセプトはとても面白い.それらの造作家具は収納スペースになったり,子どもの遊び場になったり,机になったりと用途と時間の必要性に合わせて役割を迅速に変容させる.ただ提出図面ではこの造作家具が持っているよさが,研究しきれていない,あるいは表現しきれていないため,十分に伝わって来なかったところは残念であった.
このコンペは実際に建設されるコンペであるため,最優秀案となるためには,優れたデザインアイデアと同時に緻密な寸法感覚が要求される.多くの応募案を見ながら,未来の住まいのあり方についていろいろと考えるよい機会となった.
原田真宏
建築家/マウントフジアーキテクツスタジオ主宰,芝浦工業大学教授

テーマの「生きながら働き,働きながら生きる」はそもそも矛盾した言葉です.だって本来,「働く」は「生きる」の一部であるはずなのですから.しかし,このテーマがある強いメッセージとして成立してしまっている事実は,「働く」と「生きる」が分離してしまっている,現在の社会の問題を逆説的に明らかにしているのかもしれません.
近代は人間のさまざまな行為を各スケールで分離し整理してきました.都市であれば用途地域でのゾーニング,建築であればリビング/寝室/廊下といった機能によるプランニングといったように.近代化とはそれまでの曖昧な世界をデジタルに定義・整理し,曖昧さを排除していくことにその本質があったのかもしれませんが,そもそも私たち人間という存在は曖昧なものです.商売をしながら住まう住居併用店舗による商店街は活気があるし,リビングのソファで子どもの朝の支度を見守りながら仕事のテキストを書くなんてことも豊かな日常ですよね(今まさにそのシチュエーションです).
つまり,都市にも建築にも,従来のデジタルな機能分離主義を越えて,さまざまな「〜ながら」を許容するような,豊かな「階調」のある計画へと進歩的に回帰する必要があるのではないかと思うのです.
三井住空間デザイン賞を受賞した川見案はまさにその階調の多様さと質の高さが際立っていた提案です.仕事/生活の比率を穏やかに変化させながら全体が構成されていて,何処かには時々の自分に適した空間が見つかりそうです.中心に水回りコアを配して回遊型動線としたことで,経路に選択性が生まれていることも,異なる状況を持つ家族間の調整を助けてくれそうでリアリティがあります.
惜しくも優秀賞となった池田案など,明快でエッジの立ったコンセプトを持つ案にも正直心惹かれました.しかしどこか懐かしさも覚える,おだやかな「階調」という概念に,未来の可能性を見出せたこと.そこにコンペとしての収穫を感じています.
成瀬友梨
建築家/成瀬・猪熊建築設計事務所主宰

夫は都心で働き,妻は郊外のマイホームで専業主婦,という高度経済成長時代の幸せのかたちは,もうみんなが目指すものではなくなった.単身世帯の増加,終身雇用の崩壊,少子高齢化,生涯未婚率の増加など,生き方・働き方が多様化し,選べる時代にあって,どう生き,どう働くか,そしてそれを空間でどうサポートするのか,が問われたコンペだった.1次審査を通過した5案のうち,働くこととその他の生活とをはっきり分ける案と,その逆で,できるだけ溶け合った状況を目指す案があったが,私が魅力を感じたのは,両者の間をつくろうとしている案だった.川見案は玄関脇,ダイニング,窓際のリビング,廊下の本棚の脇などに書斎コーナーが散りばめられていて,自宅で仕事をする人が,1日の時間の変化の中で気分に合わせて場所を選び取りながら仕事をしている様子が思い浮かんだ.対して,池田案は,仕事や食事などさまざまに使うことのできる大きなテーブルがプランの中心をつくり,そこに家族や仕事仲間が集まっている風景が思い浮かんだ.大きく明るい中心の空間に対して,個室はアルコーブのように取り付いている.玄関を開けると眺望が一気に広がるのも,41階という今回の住戸の特徴を活かしており高く評価された.案の鮮やかさであれば池田案の方が際立っていただろう.それでも川見案が選ばれたのは,空間に豊かな階調があることで,住宅としてのプライバシーや居心地のよさを失うことなく,住まいを拡張しているからではないだろうか.何かを犠牲にして実現する新しさではない,優しさに溢れたプランだ.ひとりで過ごすのも,2〜3人の家族で過ごすのも,あるいは人を招いて大勢で過ごすのにも,さまざまに変化させて使うことができそうなのは,この案が持っている力ではないだろうか.実現に向けては,シンプルなだけに,質感が非常に大事になってくる.素材や光の状態などを十分に検討しながら,丁寧につくっていってもらえたらと思う.
稲田信行
三井不動産レジデンシャル 横浜支店 開発室 室長

このたび記念すべき第10回を迎えた当コンペは,顕在化した顧客マーケティングに基づいて企画・設計されることの多い民間デベロッパーによる「分譲マンション」という集合住宅において,若手建築家の自由な発想や新しい生活空間への提案を実際の分譲住宅に実現させるユニークなコンペであり,今回も多くの方に応募いただき厚く御礼申し上げます.
世の中において「働き方改革」の流れが加速し,在宅ワークやダブルワークなど多様な働き方が選択できる環境が整い始めてきている中で,すまいのあり方も従来のOFFの空間だけではなく,さまざまなかたちで働くためのONのスペースや機能が入り込んでくるのではないかという仮説に基づき本テーマを設定しました.
応募いただいた185点の作品は,まさに多種多様な新しいコンセプトのすまいのあり方が提案されており,審査委員としても個々の提案の独創性を評価する一方で,実際の分譲住宅として実物をつくり上げる実現性を加味しながら入賞作品5点を選定しました.
入賞5作品の公開2次審査では,約80m2の広さと3,500mmの階高を活かしながら,すまいの中で働くスペースをどのように配置していくのがよいかという点において各々ユニークな提案がなされ,提案者がイメージする「ワーク ライフ インテグレーション」のバリエーションの豊かさに感心させられた次第です.
三井住空間デザイン賞を受賞した川見案は,80m2の空間の中で交流する(&働く)土間空間と休息する(&寝る)板の間空間の間に切り替え空間としての明るいリビングが配置されており,他4案と比べて空間利用の可変性や柔軟性という点で優れていると思います.ただ,惜しくも優秀賞,佳作受賞となりました4作品も各々独自性のあるライフスタイル提案がなされており,たいへん興味深く審査させていただきました.
今後も本コンペを通じて,時代のニーズに合った「すまいとくらし」を建築家のみなさんと共に提案してまいりたいと思います.