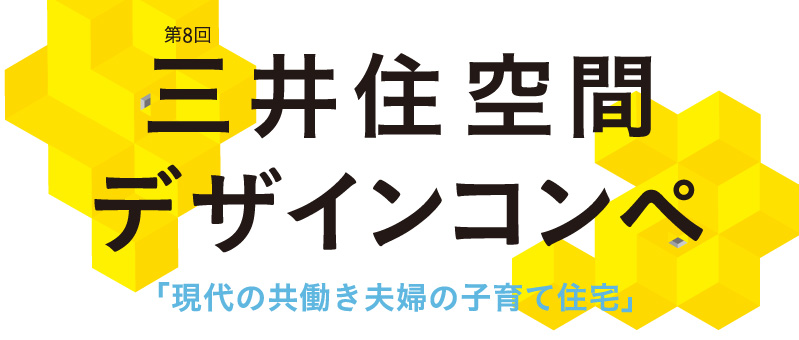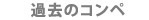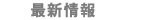審査講評
古谷誠章(建築家/早稲田大学教授)

今回の住戸タイプは東南角の両面採光で,プランも整形の申し分ないかたち.さぞかし考えやすいだろうと思ったが,ふたを開けてみると案外と似たような提案が多く,何パターンかのグループ分けに収まってしまう感じだった.しかも前回の当選案が,住戸の真ん中に何もないボイドを置くものだったので,それに類したものもいくつも見受けられた.さらに多かったのが,そこに長いテーブルを置いてその周囲を巡る案,逆に中央に収納や居室をコア的に置いてその周囲を回遊する案などで,いずれもその代表格が最終選考に残っている.
こういうコンペではどうしても,それら多数派の中からは1点ずつしか最後に残らないから,1回戦からかなりの激戦になる.しかも往々にして最後の最後にグランプリに届かない.逆に他に類のないユニークなものはシード権があるようなものだ.今回の結果はまさにそれを絵に描いたようなかたちになった.
最優秀となった小野案は,住戸を3列のゾーンに分けて,西側の壁際に水回り,東側を寝室サイドに,そしてその間は玄関から南側の大型テラス窓までを結んだリビング・ゾーンとする提案で,パターンとしては「三枚下ろし」のグループに入りはするが,壁の屈曲を使って中央の空間を「ラッパ」型にしたところに個性が出た.おそらく逆パースの効果で,玄関を入った瞬間に開放的なテラスまでの空間を身近に感じると思う.こうなると,いくつも難点もあるのだが,なかなかはずせない.結局,決勝戦にまで勝ち残った.
決戦相手の星+上案が真ん中に収納を置く「回廊」グループの曲者で,かなりの激戦を勝ち抜いてきていたのだが,最後に力尽きた感がある.甲子園でもないのに妙な感じだが,推薦する審査委員の側の,応援の体力が尽きてくるのだろうか.僕個人としては鈴木俊祐案もかなり惜しい.「寝場所は固定しなくてもいいじゃない!」と言い切ってもらいたかったが,もう一歩のところで涙をのんだ.
光井純(建築家/光井純アンドアソシエイツ,ペリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン代表)

第8回目と回を重ねてきた今回の住空間コンペでは,応募者も相当アイデアをつくりこんできており,それぞれの案に大変な密度を感じることができた.公開審査でも私自身最後までどの案に投票するか,かなり悩まされてしまった.それぞれの案に対して,斬新さ,実現性,今後実施設計に進んだ時の展開について相対的に考えなくてはならない.建築家としての価値判断が社会の価値基準から孤立しないことが審査の重要なポイントであると考えた.
最終に進んだ案の中で私が1回目に投票したのは,鈴木俊祐案,小野案,佐本+斉案であった.坂本+梅田案,阿部+加藤案にも心を惹かれたが,1回目の投票では審査委員は3票という限られた投票権しかもっていないこともあり,残念ながら選択することができなかった.最終投票では小野案と佐本+斉案が実質一騎打ちとなり,4人の審査委員はそれぞれ一票を投じて,3対1で小野案が最優秀賞に選出された.細かい点で小野案は,今後検討すべき改善点がいくつか指摘されたが,私としては今後の協議の中で調整できる範囲であると考えて投票した.2位となった佐本+斉案は暮らしの中央に共同の収納空間を配置するユニークで斬新な案であったが,壁面の扱いに工夫が足りず,改善はかなり難しいと判断した.審査の度に思うことだが,このコンペは実施コンペであるため,審査する側も現実性と斬新さを両立させる難しい判断を迫られる.
今回のテーマは「現代の共働き夫婦の子育て住宅」であるから,変化に対する配慮,限られた空間を広く見せる工夫,ON/OFFの切り替えの巧みな空間構成等,いくつかの点が重要視されたと思う.惜しくも最優秀にならなかった案にもたくさんの啓発的な考え方が込められており,これまで選外の設計者も主催者との事業に繋がった実績もあることから,このコンペの持つ社会的意義や広がりは大変大きいと思っている.
渡辺真理(建築家/法政大学教授)

「共働き夫婦」のための「子育て」住宅というテーマは分譲マンションのテーマの中でもいわば王道であるし,対象住戸の12m×7m(84m2)の矩形という住戸の平面寸法も規準的である.さらに南向き角部屋,駅にも大型商業施設にも至近距離という恵まれた条件が加算されて,ここには日本人の現代の住まいの規準と理想が条件設定されている.
2次審査に残った8案は1次審査の588案の中から選出されているだけにそれぞれレベルの高い提案だったが,発表を聞きながらいくつか共通性があることに気づいた.「寝室はあるが個室がない」のである.視線をさえぎることで個人のプライバシー確保とし,音のプライバシーよりは家族の気配を優先するというスタンスは,nLDKのnが,個人のプライバシーのための「個室」というより,子ども部屋という名前の「個室=孤室」となり,家族間に「共有するもの」が失われてきているという危機意識の表れなのかもしれない.
鈴木俊祐案の長さ9mのテーブルも家族の居場所をはっきりと提示しようという設計者の意思の表れとするならとてもよく理解できるし,佐本+斉案の提案も収納室を部屋の中央に置くことで収納=家族の物品の置場を共有するのが狙いであることがわかる.
住まいを家族のために開くことは大賛成だが,家族だけのための空間となってしまうと住まいは社会から閉ざされたものとなりかねない.小野案は住まいを水回りと寝室と「通りみち」(共有空間)に大きく3分割し,南側の開口部に向けて「通りみち」が開いている.住戸内を貫通する対角線状の通りみちは,部屋を広々と感じさせ,開放感のある,気持ちのよいミチとなることが期待できるし,室内空間がミチと呼ばれているように,そこが家族だけでなく外部社会の延長としても成立できる可能性があるのではないかと考えられる.
住まいの提案とは,個人と家族と社会のバランスを住まい内部にどう表現できるかであることをいまさらのように感じさせられた.
井上徹(三井不動産レジデンシャル取締役専務執行役員 開発事業本部長)

時代のニーズにあった「デベロッパーと建築家・デザイナーとの新しい関係」をつくることを目的とした三井住空間デザインコンペも,今年で8回目を迎えることができました.今回も多くの方々にご応募いただき,大変喜ばしく思っております.
第8回目は,「現代の共働き夫婦の子育て住宅」をテーマとして,時代とともに増え続ける共働き夫婦が,自宅で過ごす限られた時間のなかで子育てや家事をし,充実した豊かな暮らしを送ることができる空間を提案していただきました.
今回のコンペでは,われわれデベロッパーのnLDK住戸の常識にはない提案が数多く見受けられました.特に「廊下」について,単なる通路としての廊下ではなく,廊下にあたる空間に何らかの機能を持たせる提案が多かったことは印象的でした.その際たるものとして,最優秀の小野案は,「寝室」と「水回り」以外の部分を「通りみち」と呼び,食事をしたり,遊んだり,仕事をしたりするさまざまな機能を持たせつつ,住戸内でありながらソトとの繋がりを感じさせる空間にする仕掛けをちりばめていました.
玄関からバルコニーまでを一気に見渡せる「通りみち」の広がりは,課題住戸が東南角であることの日当たりのよさも加わり,完成したらさぞ明るく,開放感のある空間になるだろうことが目に浮かびます.
また,居室が完全に独立しておらず,緩やかに繋がっている提案も多く見受けられました.確かに,暮らしの中で家族の気配を感じていることは大切かもしれませんが,いつもその必要があるのかどうかは,遮音性や空調設備との取り合いなども含め,深く検討していただく余地はあるかと思います.
最優秀の小野案は,「パークホームズLaLa新三郷」で実際の住まいとして実現させていただきます.今後とも当コンペを通じて,時代のニーズに合った「暮らし」のイメージでマンションが語られる視点を提起し続け,建築家の方々とともに,常に時代に呼応する「住まいと暮らし」を提案して参りたいと考えております.